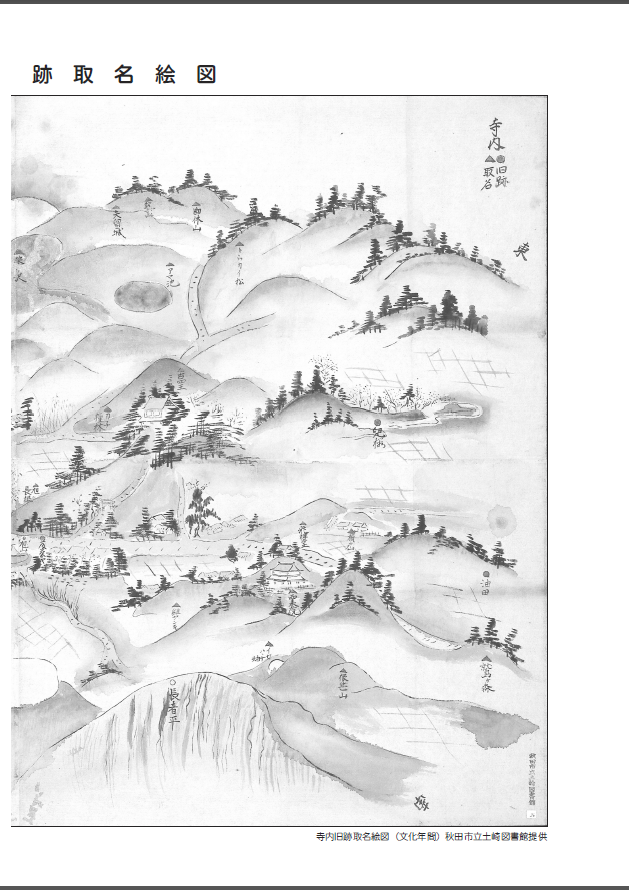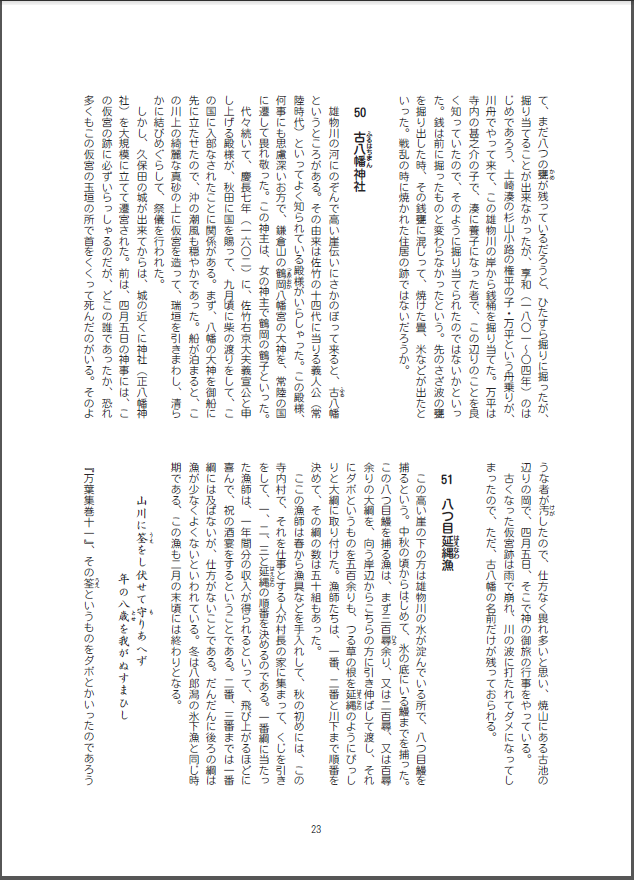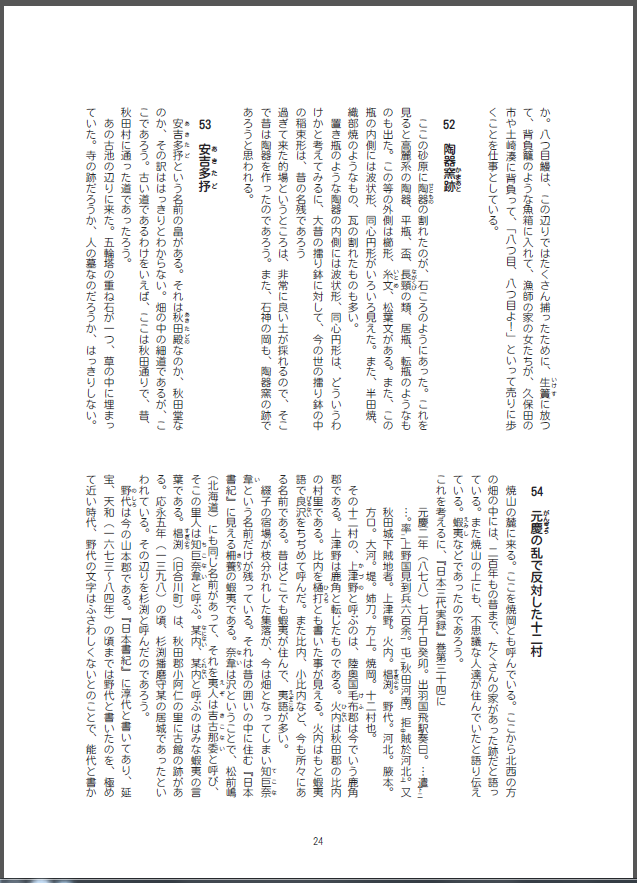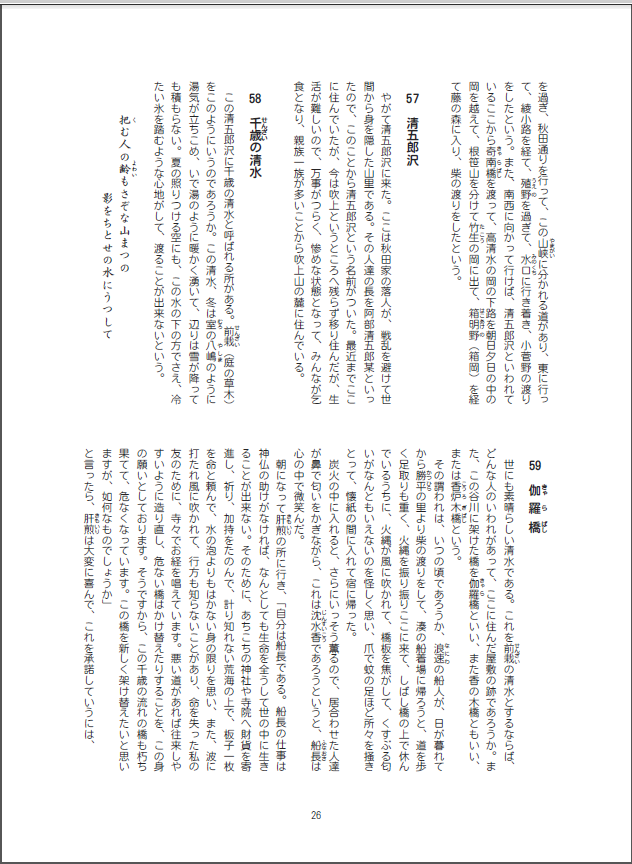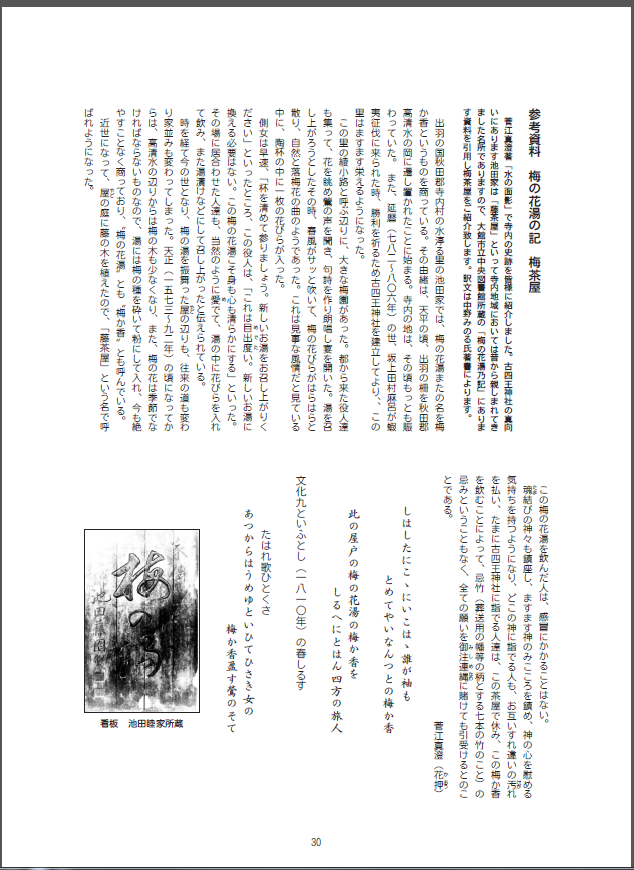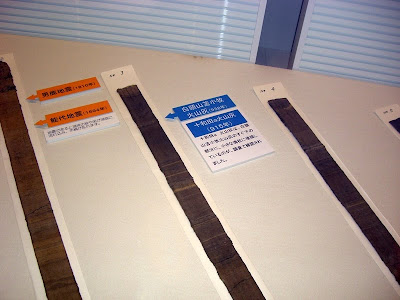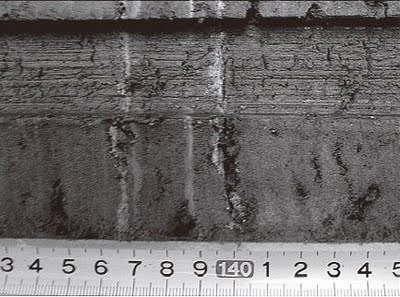秋田県に関することを抜き出します
京都・清水寺の田村神社
『「日之本文書」とエミシ・アテルイの戦い』より
坂上田村麻呂
軍神にまで神格化された坂上田村麻呂
倭国公認史である『日本後紀』では、坂上田村麻呂について、次のように祭り上げられている。
「正四位上(坂上)犬養の孫、従三位(坂上)苅田麻呂(かりたまろ)の子である。その先の阿智使主(あちのおみ)は、後漢の霊帝の曾孫である。田村麻呂は赤面黄鬚(おうしゅ 黄色のひげ)、勇力は人を超え、将帥の器である。桓武帝はこれを壮として延暦二十三(八〇四)年、征夷大将軍に召す」
田村麻呂は、倭国では国家的歴史的英雄であり、征夷大将軍の代名詞となり、軍神として神社にも祀られ、毘沙門天(びしゃもんてん)の化身とまで言われる。延暦十六(七九七)年には「征夷大将軍近衛権中将陸奥出羽按察使従四位上兼陸奥守鎮守将軍」という長ったらしい肩書が付くようになる。伝記によれば「怒って眼(まなこ)を巡らせば、猛獣もたちまち倒れ、笑って眉を緩めれば、子供もすぐになつく」などと文字どおり伝説的に描かれている。彼の先祖をさらに逆上っていけば、スキタイ・サカ族の渡来人にまで至るだろう。「赤面黄鬚」はそこからくるだろう。スキタイ・サカ族とは、中央アジアに発生した騎馬民族であるが、イスラエル系などの血脈や文化が浸透している。
しかし、『日之本文書』の田村麻呂への評価はこれとは正反対である。「奥州隠誌大要」[奥州殲隠史抄]は、田村麻呂について、次のように述べている。
「坂上田村麻呂と父親の刈田麻呂の父子は、漢の霊帝の後裔といって自画自賛をたくましくして、大和朝廷を威圧するのはしたたかである。また、倭朝に和睦策を受け入れさせ、奥州に和平の官人を入れたのも、狙うのは産金貢馬のみの利益を得るがための手段である」
坂上田村麻呂が「征夷大将軍」を名乗ってから、日本の最高権力者は、一時期の中断はあったものの、征夷事業が中止された後も、江戸時代まで約一千年間もこの称号を誇らしげに使った。単に軍事の最高権力者であるだけでなく、政治の最高権力者でもあり、征夷大将軍府は天皇府との二重権力の一方を担っていた。いかに「蝦夷征伐」が大和朝廷にとって、重要な事業であったかがわかるだろう。しかし、『日之本文書』も主張しているように、征夷大将軍の肩書を背負っていても、征夷に勝利した将軍は一人もいないのが実態なのだ。
桓武王朝は百済王族の亡命政権でもあった
いわゆる「蝦夷征伐」を敢行した桓武天皇とは何者か。彼の父親、光仁天皇(白壁王)は百済亡命貴族、百済王文鏡であり、母親の高野新笠(たかのにいがさ)も百済王の武寧王(ぶねいおう)の血を引いている。桓武天皇は純粋な百済人であり、純粋な渡来人である。桓武は父親である光仁天皇が死んだときに「天皇哀号」、つまり「天皇がアイゴーといって悲しんだ」と『続日本紀』にも記されてある。彼は百済の言葉、母国語で泣いたのである。
桓武王朝は、百済王族と藤原氏(スキタイ・サカ族が主流)によって要職を占められ、そのバックの後見人として秦氏が控えていた。百済王族は、白村江(はくそんこう)の戦いに敗北し、日本に亡命したが、新羅系王朝で冷遇され、百済系の桓武王朝になってようやく厚遇されるようになった。百済亡命貴族の主な者を挙げてみよう。武鏡が敬福の子供であり、俊哲が孫であり、教俊がひ孫といった具合に、桓武王朝の主要なポストが、一族郎党によって固められていた(括弧内は主な役職)。
百済王敬福(陸奥守、常陸守、宮内卿、外衛大将)
百済王文鏡(内舎人、出羽守、光仁天皇)
百済王武鏡(主計頭、出羽守、周防守)
百済王俊哲(陸奥鎮守将軍、下野守)
百済王教徳(上総守、宮内大輔、刑部卿)
百済王英孫(陸奥鎮守権副将軍、出羽守)
これをみれば、百済の王族が、陸奥や出羽の「蝦夷征伐」「陸奥経営」の最前線に立ったことになる。そして文鏡のごときは光仁天皇に成り上がっているのである。それぞれ従五位上とか従五位下とかの位が与えられている。
桓武征夷の目的は百済王族のための土地と金属の略奪と軍馬の無力化
大和朝廷はなぜ、「蝦夷征伐」を敢行したのか。その理由はひとつではない。大きなものは、以下の五つである。
第一の理由は、五百年以上にもわたって、日本列島の支配権をめぐって死闘を繰り広げてきた日高見国(荒覇吐国)を打倒し、倭国の安定した支配権を獲得することである。日高見国は、列島の先住民、耶馬台族、荒覇吐一族、物部一族、新羅系亡命者などからなる強力な連合国家であり、渡来系の豪族連合国家としての倭国にとっては、九州王朝と並び最大のライバルであった。
第二の理由は「渡来人」という名の「亡命貴族」「亡命王族」のために土地、奴隷を獲得することである。白村江の戦いに破れた百済王族、貴族は、念願の光仁、桓武の百済王朝ができると、彼らは国家の全面的バッグアップを受けて新天地をめざした。日高見国の北上川流域は「水陸万頃」、水田稲作に適した広大な土地が広がっていた。
第三の理由は、武器や農具や工具としての鉄の生産地を抑えることである。鉱山資源、製鉄技術、鉱山労働力の確保を狙ったのである。日高見国は日本でも有数の鉄の生産地であった。荒覇吐一族は大和朝廷経由ではなく、古くから独自の、北方経由の、南海シルクロード経由の製鉄技術を習熟していた。
第四の理由は、権力や富の象徴としての金の産地を押さえることである。八世紀に入って、大和朝廷は陸奥の黄金に注目しはじめた。北上川流域の栗原、和賀などの砂金である。朝廷は貢金を調庸の中に組み込み、献納させた。産金、冶金の業にも渡来人が進出した。
第五の理由は、戦闘用、農耕用の馬の無力化である。ここでは軍馬の重要性について詳述しておこう。馬も鉄同様、エミシの武器になった。エミシは馬上から、片手で使用できる蕨手刀を巧みに操り、朝廷軍と互角以上に戦った。陸奥国は「馬飼の国」ともいわれ、広く馬の放牧がなされていた。その馬はユーラシア大陸の騎馬民族国家である靺鞨(まっかつ)国などから取り寄せたものが多かっただろう。
『東日流外三郡誌 第四巻』[靺鞨国往来]では「靺鞨国の酋長が東日流に馬を積んで交易した。東日流の海辺の広野は、馬また馬に増殖した」と述べられている。前述のように阿弖流為、母礼は山靼地方の靺鞨族の出身の可能性がある。
大和朝廷による「蝦夷征伐」が本格化すれば、馬は朝廷側、エミシ側双方とも軍馬としての重要性も出てくる。馬が抵抗する「麁蝦夷(あらえみし)」に渡れば、朝廷側にとって脅威となる。
『続日本後記』は「弓馬の戦闘となると、これは蝦夷にとっては生まれつきの戦法であって、攻める内民たちは十人をもってしても、蝦夷の一人に勝つことができない」と認めている。
『日本後紀』では「軍事用として馬は一番重要である。にもかかわらず安易に取引されて、価格が高騰し、混乱が続いている。強壮の馬は取引を禁止し、警護に備えよ」という禁令が布告されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
田村麻呂は武力では制圧できずに謀略を仕掛ける
「北鑑 第十二巻 十九」の阿弖流為の記事も、田村麻呂による謀略について描いている。「江刺の翁(おきな)、物部但馬(たじま)という人物から聞き書きしたものである」という寛政六年九月十三日の秋田孝季の署名がある。
「丑寅日本国の五王に通称アトロイという王がいる。大公墓阿弖流為または阿黒王、悪路王と倭史は記している。
大和朝廷の朝議は、相謀(あいはか)って坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命した。すでに官軍は討伐行を羽州から鬼首(おにこうべ)峠を越え、日高見川において千三百三十六人の兵を殉死させ、阿弖流為軍は八十九人の殉死あるのみで、官軍は全ての兵糧を奪われた。よって田村麻呂は軍謀について和睦を先としていた。田村麻呂曰く。
日本将軍五王に朝議の趣旨を申す。互いに戦いの原因を作ることなく、和をもって東西の睦みを護ろうではないか。よって率いてきた者が宿泊する柵の造営を許可願いたい、と多賀城、玉造柵、伊治城、雄勝(おがち)柵、胆沢(いさわ)柵、徳丹(とくたん)柵、払田柵、秋田城跡に市場を築くことを請うた。
ときに阿弖流為はひとり合点(がてん)がいかず、日本将軍の安倍安堯(やすあき)に申したところ、市場ならばとして、濠がなく、柵がないように築くという条件を約束して許可を得た。しかるに阿弖流為が一見要塞としか見えない市場造りに不審をいだいて、これぞ倭朝の議に偽りがないかと田村麻呂に何度か問うたが、田村麻呂は曰く、我も倭の大王に言わしめれば蝦夷なり、何事あって丑寅日本を憎むだろうか、とその都度答えた」
これを裏付けるように田村麻呂によるしたたかな慰撫作戦、謀略作戦が実行されたのである。田村麻呂は仏法に公布を装って、武装移民を多賀城や胆沢柵に進駐させ、和睦と称して、阿弖流為を拉致し、胆沢から京都へ引き連れる策略を考えていたのである。
『總輯 東日流六郡誌 全』[田村麻呂奥州経略]においても、田村麻呂が蝦夷征略の一切を任せられ、武器を持たない民団を派遣し、日之本将軍安倍安東から日高見国での駐在を許され、各地に神社仏閣、城柵を建設した。これに阿弖流為、母礼が「戦いなき心の侵略」「日高見はみな倭のようになってしまう」と疑念をもち、それを安倍将軍に告訴したが、聞き入れられなかったとしている。
延暦年間には安倍安国、安東、国治(東)、安堯らの日之本将軍の名が『日之本文書』に出てくるが、安倍一族の年譜と照らし合わせると時代的なズレが見られ、その存在自体が希薄に感じられる。田村麻呂と直接対峙していないためか、日之本将軍による彼に対する警戒心が乏しかったように感じられる。大和朝廷による攻勢によって、荒覇吐国家と日之本将軍の統率力が弱まったようにも感じられる。日之本将軍の田村麻呂に対する警戒心が足りなかったことが、大きな悲劇を生み出すことになったのである。