5月8日は胡四王神社の祭典です。またおもしろい「のりつけ棒」が見られました!

1、古四王神社祭典
子供たちも参加(学校を休んでも参加できる)し、神輿も出ています。六角形に鳳凰がついた立派なものです。作画は由緒ある神社です。
2、不思議な「のりつけ棒」
中央の棒が「糊つけ棒」。直径8㎝くらいの杉の棒です。白い部分が米から作った糊。この糊のつく具合で豊作を占うというのです。時代が経っていますからそうなのでしょう!! 本当は下記のようなことだと推定しています。
3、「のりつけ棒」は「糊つけ矛(ぼこ)」
「寺内町史」には「のりつけ棒」は「糊付矛(のりつけぼこ)」とあります(p95)
矛と言えば「イザナギイザナミの国生み神話ですね」・・・古事記なんですよ!
4、平田篤胤「霊の真柱」より
古の伝えとは「古事記」のことです。
古の伝えに曰く、そこで、天ッ神の諸々の神々のお言葉で、イザナギノミコト・イザナミ ノミコトのお二柱の神に向かって、「この漂える国を、造り固めなされ」と仰せられ、アマノヌボコをお授けになり、ことを委ねられたのです。 そこで、お二柱は天の浮き橋にお立ちになり、そのヌボコを下に向けて指し下ろして、流れ漂っている青海原を、コヲロコヲロと掻き回し掻き鳴らして引き上げなされました。その 時に、ヌボコの先からしたたり落ちた塩が、重なり積もりに積もって島になりました、これがオ ノゴロ島です。 その二柱は、その島に天降りなされて、天ッ神より賜ったアマノヌホコ突き立て、国の御 柱として見立て、また八尋殿(やひろとの)を見立てなさったのです。故にそのヌホコは後で小山となりました。 |
第五図

これより次々の図には、天に成坐す 神、地に成坐す神たち、その図に用があるときのみ挙げて、絵は省く。
三大考には天と地と、この時なお連 なりたる状態に書けるは間違いな 理由は下に記す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●この天ッ神の諸々の神々のお言葉で、お二柱の神に、「この国土を固めなされ」と仰せられた時は、天と地とは既に切り離れた頃のことで
す。それはどうして分かるのかといえば、天ッ神のここでのお言葉によって知ることができるのです。それは、天ッ神の諸々の神が、高く天上から見下せば、この国土の漂える様子がよく見えているお言葉だからです。「この」と指さされたことによって明らかなのです。もし、この時もなお、天と地が切り離れていなかったら、その根とある国土が漂っているとすれば、天も共に漂っているべきなのに、どうしてこの国土を指して「この漂える国」と仰せられるのでしょうか。
さて、天と地が切り離れてから、二柱の神は「天の浮き橋」でご出立して、「浮き橋」にお立ちになって、青海原を掻き回されました。
(「浮き橋」のことは、『三大考』の説とは大きく異なることは、第十図の下に詳しく述べます)
●青海原とは、やがて天ッ神が「この漂える国」とお指しになったもののことであって、それはこの国土の生まれたばかりの頃の呼び名の理由でもあります。また青海原という言葉の意味も、古史の伝えに言われ
るとおりです。
●二柱の神に、諸々の天ッ神がお授けになったヌホコとは、「玉鉾(たまほこ)と言うように、玉でもって飾ってある矛である」と師が言われたとおりです。
(ただし、古はこのような物にも玉を飾るのは通常のことであって、ただ何とない飾りと思われますが、未だに詳しくは分かりません)
さて、その玉を飾ることには、不思議な理由があります。それは五柱の天ッ神、特にムスビノカミのムスビの御霊を、二柱の神にお授けになり、国生みを成功させようと、その御璽(みしるし)のお祝い物に飾られたものです。
(これは、私が確かに考え得た説です。それは第八図の下に挙げてある、イザナギノミコトが天照大御神に、御頸珠(みくびたま)をお授けなるところで詳しく申しますので合わせてお考え下さい)
ただしこれは、玉を飾るだけでよいものを、その御矛(みほこ)をお授けになることは、その矛で浮き雲となって固まっていない青海原を、掻きならして衝き立て、中心(なかご)の固め柱としなさいとのお計らいなのです。だからこそ、二柱の神が、掻きさぐられ、自然(おのずから)に固まり出来上がったのです。そのオノゴロ島に衝き立て、国中(くになか)の御柱となされたのです。そうですから、この大地の中心は、このお授かりになった御矛(みほこ)の先なのです。
(このようにして、その柄の方は、小山となったのです)
彼の、天となるべき物は萌え上がって去り、泉となるべき物は垂れ下り、大地となるべき物の、なおフアフアとして、固まらないのを、この御矛(みほこ)を衝き立てなされることによって、締まり固まったのです。天ッ神からお授かりになった物も多い中に、矛をお授かりになったことは、大変に不思議な、深い理由がないはずはありません。
(古には戦の出発の時に、矛を授かることもこの謂われによるものです)
そうですから、この地球が広大である中で、我が御国は国土の大本であります。またオノゴロ島は、この大地を固めた、御柱たる所になります。
(一つの伝えに、「オノゴロ島を国中の御柱となす」とあるのも、これで分かります。漢(から)の書にも「天柱坤軸などというのも、この古伝が訛り伝わったものと思われます)
(これは私のブログ「務本塾 巡堂講座」からです)
「矛」とはたいへんな代物ですね・・・古四王神社とどう関わりがあるかはわかりませんが!・・・だから古四王神社はただものではないといいたいのです。田村麻呂将軍などとは全くもって関係ないし、大彦命(大毘古命)という四道将軍が祭神ということにも大きな疑問を抱いています・・・すべては大和朝廷のストーリーである「田村麻呂信仰」の一環だと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




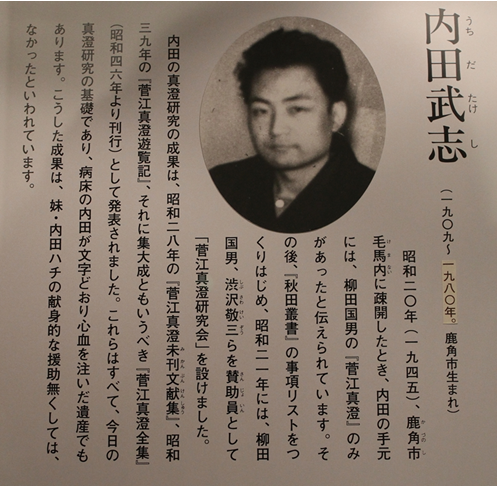

.jpg)





















