ストーンサークルは明らかに「壺」の形をとっています。
1、大湯ストーサークル
 万座環状列石
万座環状列石
こちらがよくわかります。
壺の口がよくみられます。
2、北秋田市 伊勢堂岱遺跡
このブログは「壁を突き抜ける生き方」をする人だけが共鳴できるものです。 北東北の不思議な地域、クロマンタ、大湯ストーンサークルを中心とする縄文文化の真実を探究する研究会です。 ■右側のラベル分類からもお入りください。 ◆スライドショーはクロマンタのゼロ磁場調査の様子!!


 こうした経緯の中、陸奥国支配の本拠地として多賀城が創建されるに至り、政府は、此処に、陸奥国府と蝦夷の反乱を鎮める鎮守府を設置し、陸奥出羽按察使・陸奥守および鎮守府将軍を兼任する国守を駐在させた。
こうした経緯の中、陸奥国支配の本拠地として多賀城が創建されるに至り、政府は、此処に、陸奥国府と蝦夷の反乱を鎮める鎮守府を設置し、陸奥出羽按察使・陸奥守および鎮守府将軍を兼任する国守を駐在させた。
歌枕「つぼのいしぶみ」が、こうした伝説や和歌によって後世に伝播されていく中、多賀城碑は、江戸時代になって土中から掘り出され衆目に晒された。石碑は一般に「石文(いしぶみ)」または「立石(たていし)」と呼ばれることから、発見当座も、まずはそうした呼び名であったろう。それが彼の事物と絡められて一体化し、次第に「壷の碑」と称されるようになった、というのが事の真相かと思われる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(まとめ)
・多賀城碑は江戸時代(1656~1719ころ)発見された。
・同年代に大淀三千風が「壺の石碑」と詠んでいた。(荒俣氏は水戸光圀公が決めた)
・歌学者の藤原顕昭が1190ころ、田村麻呂将軍が書いたと「袖中抄」に記した。(これが田村麻呂伝説の一貫)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・多賀城跡が古代日本の「壺」であることは「ホツマ」で納得できる。
・しかし多賀城の「石碑」は田村麻呂以降のもので「歌枕」として成立した過程はわかった。
・私が求めるのは「壺」と同時代の「石碑」のことで、歌枕でなく「枕詞」の「壺の石碑」を求めているのです。そうすれば、多賀城では納得できないのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





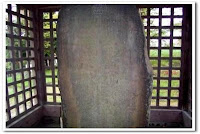







明暦二年申三月吉日[写] -- 手書図(彩色) -- -- 1舗 -- 109.1×51.7cm(17.9×12.1cm)
いわゆる行基図(ぎょうきず)。行基式日本図は、国々を丸みをおびた俵の形とし、これを積み重ね、かつ山城から諸国への経路を示すことで日本を表現することを特色とする。奈良時代の高僧行基により作成されたと伝えられ、現存する多くの行基図にもその旨記載されているが、もとより後世の仮託。ただしなぜそのように伝えられるようになったかには諸説がある。江戸時代初期まで作成された。本図においても「夫図行基菩薩所図也」との記載が序文にある。明暦2年板は最後に印刷された行基図とされるが、そのものは現存していないため、その写図である本図は貴重である。各国色別に着色し、上部を東,右を南とする。2本線で五畿七道を描く。安房の南方に「らせんこく」(羅刹国)の記載がある。


